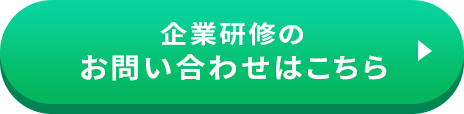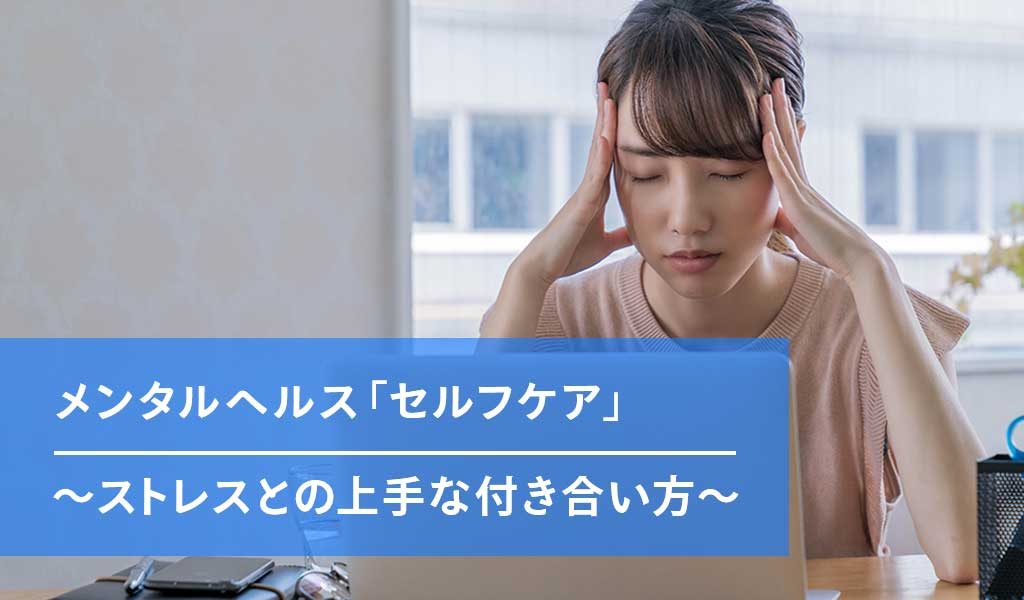ラインケアとは~メンタルヘルス対策における管理職の役割~
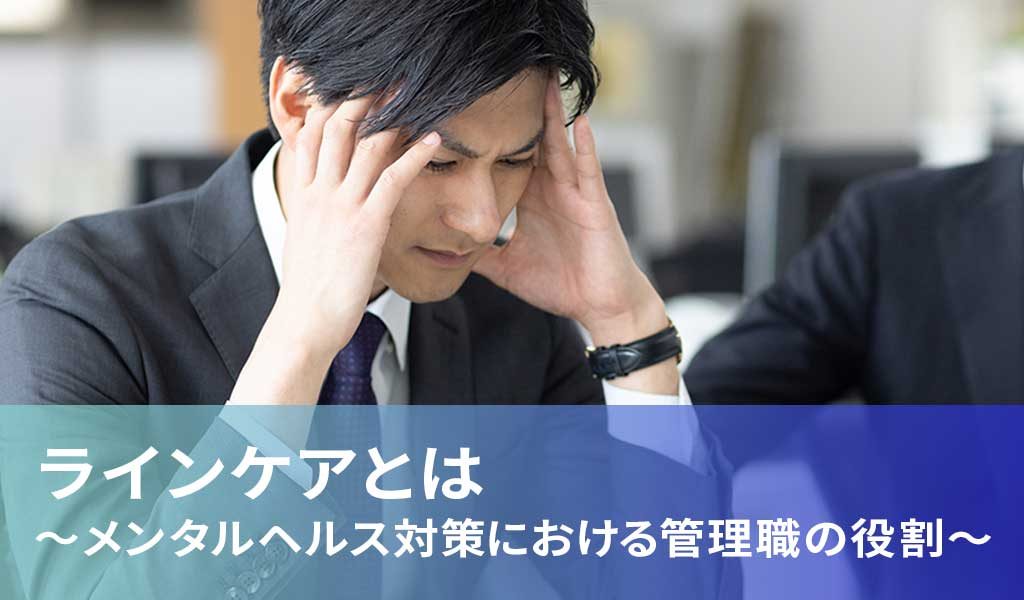
昨今、急速なグローバル化や競争の激化により、仕事や職場環境に、不安や悩み、ストレスを強く感じる労働者の割合が高くなっています。そのため、企業には適切なメンタルヘルス対策の実施により、社員の心の健康のケアが求められています。厚生労働省は、メンタルヘルス対策の推進のため「4つのケア」(※詳細は下記参照)を推奨しています。この中でも、職場の部長・課長などの管理職が部下の心のケアを行う「ラインケア」が特に重要だとされています。
そこで今回は、メンタルヘルス対策の一つとして、管理職が取り組むべき『「ラインケア」が重要視される理由と具体的な実施ポイント』をご紹介します。
メンタルヘルス対策の必要性
なぜ企業は、メンタルヘルス対策を行わなければならないのでしょうか。その一つとして、「生産性の維持と低下の防止」が挙げられます。メンタルが不調になると、業務面、行動面で様々な異変が現れ、本人の作業能力が落ちるだけでなく、周囲にも悪影響を及ぼしかねません。また、メンタルの不調に陥る人の多くは仕事熱心であるため、企業にとっても貴重な人材を失うことになります。
さらには、2020年6月から改正労働施策総合推進法(通称:パワハラ防止法)が施行(中小企業では2022年4月から)されたことにより、企業は防止策を講じるとともに、パワハラを起こさせないように指導することが義務付けられました。そのため、パワハラの被害者に対するケアはもちろんのこと、加害者になり得る社員に対しても、未然に防ぐためのケアを行うことが必要です。
「4つのケア」とは
厚生労働省の『職場における心の健康づくり~労働者の心の健康の保持増進のための指針~(2020年)』によると、職場におけるメンタルヘルスケア対策として「4つのケア」が必要だとされています。
セルフケア
労働者自身が主体となり実施するメンタルヘルス対策で、メンタルヘルスやストレスに関する知識を身につけることで、自らストレスに気づき、対処していきます。例えば、休日に趣味に没頭する、友人と話をする、日記をつけるなどによりストレス解消に繋げることや、ストレスチェックにより自分の状態を知ることも、セルフケアに含まれます。日常的にセルフケアを行うことで、自分のメンタルをコントロールすることが可能になります。趣味やストレス発散法が多ければ、その分セルフケアの効果が期待できるため、1つでも多く見つけ、定期的に実行することが大切です。
ラインケア
職場の管理職が主体となり、職場環境の把握・改善の実施や、社員からの相談を受けることで、上司が部下の心のケア行うことです。社員の定着率アップや休職防止対策としてラインケアを行うことは効果的です。部下のいつもと違う状態に気付くことが重要なポイントですので、普段からコミュニケーションをとり、それぞれの個性や特徴、労働環境などを把握するように努めましょう。また、相談を受けるだけでなく、職場環境改善に取り組んだり、休職希望者へ対応したり、職場復帰への支援なども行います。
事業場内産業保健スタッフによるケア
人事担当者や産業医などが主体となって実施するメンタルヘルスケアで、セルフケアやラインケアが効果的に実施されるように、社員や管理職に対する支援を行います。企業のメンタルヘルス増進を目的とした「心の健康づくり計画」の中心的な実施主体となり、以下のようなことを実施していきます。
- 具体的なメンタルヘルスケアの実施に関する計画立案
- 個人の健康情報の管理
- 事業所外資源とのネットワーク形成や窓口業務
- 事業所内産業保健スタッフとして休職者に対する職場復帰支援
事業場外資源によるケア
外部の医師や各種カウンセリングサービスなどの、事業所外の専門機関や専門家が主体となって実施するメンタルヘルスケアで、主に事業場内産業保健スタッフに情報提供を行うことや、相談内容を会社に知られたくない社員からの相談に対応します。社内の人に相談しにくい悩みの場合や、社内に相談できる制度がない場合に利用されることが多いです 。

効果的な3つのラインケアの取り組み
ラインケアで実施すべき内容は、具体的にはどのようなものがあるのでしょうか。3つご紹介します。
①早期発見のための観察
ラインケアで大切なのは、部下の「いつもとの違い」にいち早く気づくことです。不調を早期発見するためには、日頃からコミュニケーションを取り、自分の部下の行動や人間関係などに気を配っておくことが大切です。部下に以下の変化があったら特に注意が必要です。
- 遅刻、早退、欠勤が増える
- 休みの連絡がない(無断欠勤がある)
- 仕事の能率が悪くなる。思考力・判断力が低下する
- 報告や相談、職場での会話がなくなる(あるいはその逆)
- 表情に活気がなく、動作にも元気がない(あるいはその逆)
- ミスや事故が目立つ
- 服装が乱れたり、衣服が不潔であったりする
(『職場における心の健康づくり~労働者の心の健康の保持増進のための指針~(2020年)』より抜粋)
これらの部下の変化に気づいたら、声を掛け、話を聴き、場合によっては産業医やカウンセラーなどへの相談を勧めましょう。「いつもと違う」部下への気づきと対応は、心の健康問題の早期発見・早期対応として重要です。
②気軽に相談できる環境づくり
部下が自身の変調に気づいたときに、気軽に相談できる環境が必要です。そのためには日頃から、部下との信頼関係を築いておくことが重要です。また、面談の機会を定期的に設けたり、専任の相談員を設置したりすることも有効でしょう。ラインケアの面談時には、周囲に声が聞こえにくい静かで落ち着いた環境を用意し、穏やかな表情で接するなど、リラックスした雰囲気を作ることが大切です。相手の話をしっかり聴かないまま、励ましや説教といったコミュニケーションは逆効果ですので、耳を傾けて、熱心に聞く「傾聴」がポイントになります。
③休職者の職場復帰への支援
部下の心の健康状態に気を配り、悪化を未然に防ぐことがメンタルヘルス対策ですが、ラインケアには、万が一休職者が出てしまった場合に、スムーズに職場復帰できるように支援をする役割もあります。復帰する際には、できるだけストレス要因をなくし、心的サポートや業務負荷の調整、周囲の理解が不可欠です。メンタルヘルスの不調は、病気やケガと異なり、回復や完治が不明瞭で、再発の可能性も秘めています。復職者が、休職したことに対して罪悪感を持ってしまえば、さらに悪影響を及ぼすリスクもありますし、過労によるストレスを引き起こすケースも考えられます。過度の励ましや気遣いが、逆効果になることもあるため注意が必要です。
まとめ
企業が行うメンタルヘルス対策の「4つのケア」の中でも、管理職が部下の心のケアを行う「ラインケア」は重要視されています。日頃から社員の心の健康状態に気を配り、ストレスなどメンタル不調を未然に防ぐことによって、企業の損失や生産性の低下を防ぐことができます。部下の「いつもとの違い」にいち早く気づいて対応するためには、ラインケアの基礎知識を身につけ、普段から適切なコミュニケーションをとることが重要です。
導入事例
何か起こってから、ではなく、起こる前の事前対策としてのハラスメント教育を~那須グリコ乳業株式会社~
関連する研修
-
2021.01.21
メンタルヘルス研修(ラインケア)
-
2021.01.21
メンタルヘルス研修(セルフケア)
-
2021.01.21
ハラスメント研修
関連する投稿
-
2021.01.21コラム
メンタルヘルス「セルフケア」~ストレスとの上手な付き合い方~
-
2021.01.21コラム
新入社員教育~メンター制度とは?メリット・デメリットをご紹介~
-
2021.01.21コラム
【メンタルヘルス】セルフケアで「風邪のひき始め」に気付く重要性